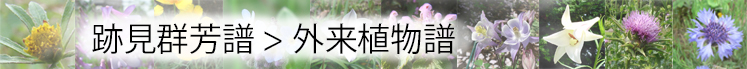
キャッサバ
学名 Manihot esculenta (M. utilissima) 日本名 キャッサバ 科名(日本名) トウダイグサ科 日本語別名 イモノキ、タピオカ、マニオク 漢名 木薯(ボクショ, mùshŭ) 科名(漢名) 大戟(タイゲキ,dàjĭ)科 漢語別名 英名 Cassava(E.), Manioc(F.), Yuva(Sp.)、Mandioca(ブラジル・パラグアイ)、Tapioca(インド)
 |
||||
| 辨 | キャッサバ属 Manihot(木薯 mùshŭ 屬)には、中央アメリカ・ブラジルを中心に約100種がある。 キャッサバ(イモノキ) M. esculenta(木薯) マニホットゴムノキ M. glaziovii(木薯膠) ブラジル原産 |
| トウダイグサ科 Euphorbiaceae(大戟 dàjĭ 科)については、トウダイグサ科を見よ。 | |
| 訓 | |
| 説 | 熱帯ブラジル原産。 根が肥大していもを作る。1株当り5-10個、直径4-10cm、長20-40cm、澱粉含有量は25-40%。 いもの皮層にシアン配糖体を含み、有毒。 |
| 南アメリカでは、B.C.800頃には利用されていたらしい。 コロンブス以後世界にひろがる。 |
|
| 誌 | イモを、加熱などにより毒抜きをして食用にする。19世紀からアジア・アフリカの熱帯でも広く栽培されるようになり、今日では世界の熱帯地方で主要な主食とされている。 |
| 跡見群芳譜 Top | ↑Page Top |

