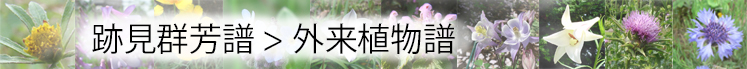せいたかあわだちそう (背高泡立草)
| 学名 |
Solidago altissima |
| 日本名 |
セイタカアワダチソウ |
| 科名(日本名) |
キク科 |
| 日本語別名 |
セイカタアキノキリンソウ、ヘイザンソウ(閉山草) |
| 漢名 |
北美一枝黃花(ホクビイチシコウカ,bĕimĕi yīzhīhuánghuā ) |
| 科名(漢名) |
菊(キク,jú)科 |
| 漢語別名 |
高莖一枝黃花 |
| 英名 |
Tall golden-rod |
| 2006/05/06 薬用植物園 |
 |
| 2010/10/06 入間市宮寺 |
 |
 |
| 2005/10/24 さいたま市田島が原 |
 |
 |
| 2006/11/01 新座市 柳瀬川 |
 |
 |
| 辨 |
アキノキリンソウ属 Solidago(一枝黃花 yīzhīhuánghuā 屬)については、アキノキリンソウ属を見よ。 |
| 訓 |
和名は、大型のアワダチソウ(アキノキリンソウ)。ヘイザンソウとは、第二次世界大戦後 九州で閉山した炭鉱に繁殖したことから。 |
| 説 |
北アメリカ原産。明治時代に観賞用に導入、第二次世界大戦後 関西地域から野生化した。 |
| 「関東南部から西の各地で勢力を振るう多年草がセイタカアワダチソウである。休耕田や適度に湿った休耕畑には、三~四年のうちにこれにおおわれた例が多い。多年草期においてススキやネザサと競争するのをしばしば見かける。乾燥した場所ではススキが徐々にセイタカアワダチソウを抑えるが、湿ったところではセイタカ優占の状態はかなり長く保たれる。これはセイタカアワダチソウの生活型の有利さのほか、浸出する他感作用(アレロパシー)物質のためでもあると考えられている。」(沼田真・岩瀬徹『図説 日本の植生』1975) |
| 誌 |
花粉病の原因植物というのは俗説。 |
|